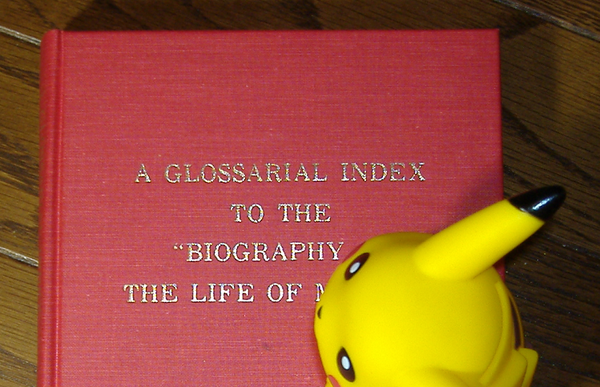ヘレン・マクロイが好きだ。海辺まで走っていって、「好きだよー!」と叫びたくなるくらいに好きだ。だからここ最近のマクロイの新刊ラッシュはとてもうれしい。
マクロイのどこがそんなにいいのか。まず本格ミステリ的な面からいうと、手がかりの出し方だ。
アガサ・クリスティとかクリスチアナ・ブランドの手がかりの出し方は、ときどきとても意地悪で、この人たちはもしかして実生活でもこんなイジワルをやってるのだろうか?と疑いたくなるくらいのものだ。しかしマクロイは違う。直球である。しかも変化球の直球である。
例をあげよう。『家蠅とカナリア』で、探偵役のウィリング博士が大時計の時刻を見て自分の時計を直す場面がある。前後のストーリーの流れから見ると唐突な場面なので、ははあここに何か手がかりがあるな、と読者はいやでも気づく。実にフェアな手袋の投げ方である。しかしこれが何の手がかりになっているのか? それがまるでわからない。あげくのはてに解決篇を読んであっと驚くことになる。
クリスティも似たことをやっていた。どの長篇でだったかは忘れたが、ある人物がカレンダーをじっと睨んでいる。ははあ何かのスケジュールが気になるんだなと思っていると、あにはからんや……しかしこのミスディレクションには、マクロイのと似ていても、意地悪さを感ぜずにはいられない。
それから『あなたは誰?』にも、後半に入ってからこれみよがしな場面がある。これも、すれからしの読者なら、クイーンや鮎川哲也が使い倒した手をすぐに思い浮かべるだろう。ははあすると第一の殺人は、鮎川哲也が某犯人当て短篇で使ったのと同じ手か? しかしそうだとすると事件全体の構図がまるでわからなくなってしまう。正しい手がかりがレッドへリングになっているという稀有のケースである。
あるいは『月明かりの男』。死体に傷がなかったという描写を読んで、あー傷がなかったのね(にやにや)とほくそ笑む読者は、終盤で大うっちゃりをくらうことになる。
あるいは冒頭の場面で読者に先入観を与えておいて、それで真相をカモフラージュするというのは本格ミステリでたびたび使われる手だが、『逃げる幻』ほどそれが効果的に使われているのは珍しいと思う。
要するにマクロイというのは、謎解きが好きな読者を楽しませるすべを、憎いまでに心得ている作家なのである。
*
第二のすばらしい点は、misfit(社会不適応者)の孤独がひしひしと迫る筆致にある。これは
前にも書いたことがあるのでくりかえさない。傑作『暗い鏡の中に』の成功はこれなしにありえないし、『殺す者と殺される者』のあまりにも無理筋なトリックを支えているのもこの筆致である。だが『ひとりで歩く女』のようにそれを(広い意味の)トリックにしている作品もあるから、転んでもただは起きない(?)というか、実にしたたかな根性ではある。
*
第三のすばらしい点は、小栗虫太郎の血筋をひいている点である。あたかも妖姫カペルロ・ビアンカの血が海を渡って降矢木算哲に流れ込んだごときものである。
たとえば『牧神の影』の激しく作り込まれた暗号に辟易する読者もたぶんいると思うが、これが虫太郎の血というものなのである。
いくつかの作品ではペダントリーが推理と解けがたく結びついている。たとえば『家蠅とカナリア』。冒頭で作者が大見得を切っているように、確かに家蠅とカナリアが真犯人を暴いている。ところがこれらは普通の人の手がかりになるようなものではない。あくまでウィリング博士専用の手がかりなのである。ちょうど虫太郎作品のいくつかの手がかりが法水専用の手がかりであるように。
『ささやく真実』の聴覚トリックもそうだし、『月明かりの男』の動機は(これは明かしてもネタバレにはならないと思うが)重酸化クロム(だったか?)である。こういう虫太郎風ペダントリ―抜きにマクロイの魅力はありえないと思う。