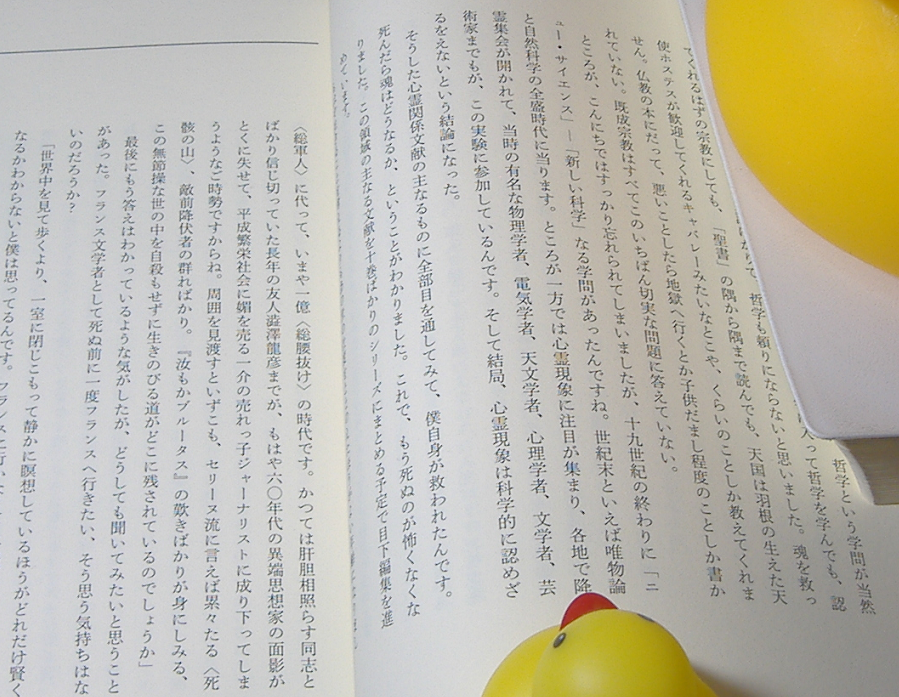女の運転するロールスロイスから白髪の青年が放り出されたのを目撃したマーロウは、そのまま青年を家に連れて帰る。そういえば少し前に『ひげを剃る。そして女子高生を拾う。』というライトノベルがあった。だがタフガイはもちろんそんなものは拾わない。拾うのは銀髪イケメンである。
この青年テリー・レノックスはマーロウに妙になつき、二人はときどきいっしょに飲む仲になる。ある日テリーがだしぬけに現われ、メキシコへの逃亡を手伝ってくれと言う。頼みを聞いたばかりにマーロウは官憲にひどい目にあわされる。
ようやく釈放されたと思ったらこんどはガラの悪い男がオフィスに来て、インネンを吹っかけてくる。何かと思ったら「おれなら賭博師がいかさまカードを切るよりすばやく国外に出してやれたのに、なのにやつはお前に泣きついた」。それが癪にさわるので文句を言いにきたのだ。
何だこれは! 読者は目が点になるだろう。まるで奥さんが夫の愛人の家に押しかけてキーとかヒステリー起こしてるみたいじゃないか。白昼堂々痴話げんかか? マーロウはこのゴロツキの腹にパンチを一発お見舞いする。ゴロツキは「おまえは妙に憎めないやつだよ、マーロウ」と好意的な(?)捨てゼリフを吐いて退散する。
ここらへんで作者チャンドラーもハッとわれにかえって、「しまった! このままではある種の女子が大喜びしてしまう!」と思った。のかどうかは知らないが、このあとわざとらしいハードボイルド調の新展開があり、やがて金髪美女まで出てくる。しかしこの登場はいかにも遅すぎる。もうすでに読者の心は前座のテリー・レノックスに食われたあとである。
ここで帯の惹句にもなっている「別れを告げるということは、ほんの少し死ぬことだ」というセリフが出てくる。それが「フランス語の言い回し」と言われていることに注意したい。OEDによるとフランス語の "la petite mort" (小さな死) が英語の文章で使われた場合、現代では特に "the sensation of post orgasm as likened to death"を意味するという。もし「別れを告げるということは~」にもこのニュアンスがあるとすれば、このときマーロウがロマンティックな気分に浸っていたとは考えがたい。もしかしたら「賢者タイム」的な意味合いさえこもっていたのかもしれない。
少なくとも最後から二番目のパラグラフの「それでも私は耳をすましつづけた」にくらべれば、かなりの温度差があることはだれしも認めるだろう。最後にはチャンドラーも、ある種の女子が大喜びしてもしかたないと観念したのだろうか。知らないけど。
ところで六年前の日記に書いたように、ラストで登場する人物の正体については三つの考え方がある。
- 正真正銘の本人であった。
- マーロウの幻覚であった。
- 亡霊であった。
今回新訳でまた読んだというのも、もしかしたらこの問題の答への糸口が見つからないかと思ってだった。やはり判然とはしなかったが、あえていえば、やはり本命は二番目ではなかろうかと思う。テリーに再会できたマーロウの嬉しさとか驚きとかが妙に伝わってこないし、最終章の第五十三章で交わされる会話があまりに整然としていてテリー本人らしくないからだ。マーロウはときどき昔の棋譜をとりだして一人でチェスをやるけれど、ここの会話もなんだかそんな匂いがする。
チャンドラーの作品にはたまにマーロウの幻覚としか思えない人物が出てくる。たとえばこの前とりあげた『さよなら、愛しいひと』でいえば、おしまいの方で出てくるモーツァルトを弾く警官である。やはりしょっちゅう頭を殴られたり酒を飲みすぎるのがよくないのではなかろうか。
【5/11付記】創元推理文庫版の裏表紙にある紹介文を見たら「〇〇した彼から」と書いてあった。ということはこれを書いた人は第一の可能性をあらかじめ排除していることになる。創元推理文庫はこういうところには抜かりがなくて、たとえば某日本作家の某長篇では女を男と錯覚させるトリックが用いられているのだが、紹介文では「その青年は」という言葉は避けて「その若者は」という表現を使ってあった。それほど表現に気を使う版元なのだから、〇〇してもいないのに「〇〇した」と書くわけはなかろうと思う。これも第二の可能性の傍証とならないだろうか。